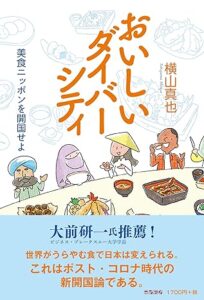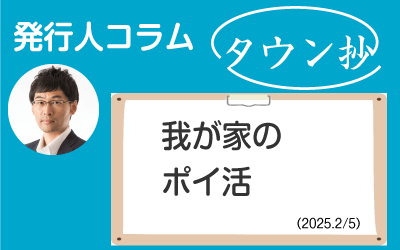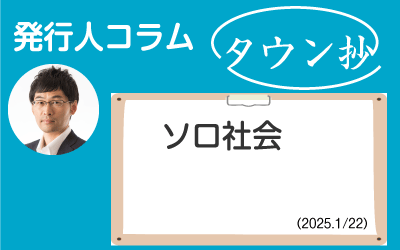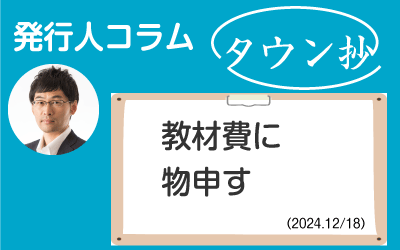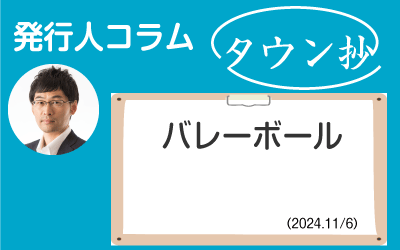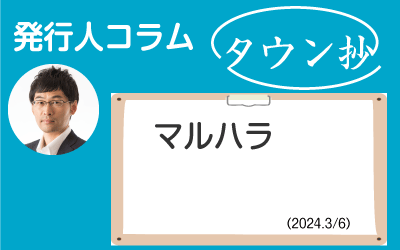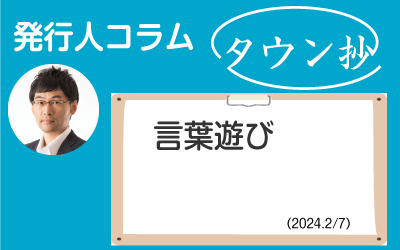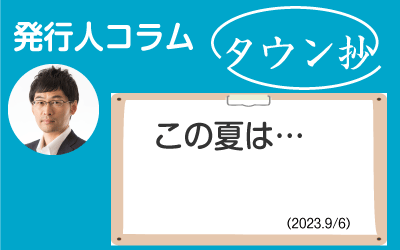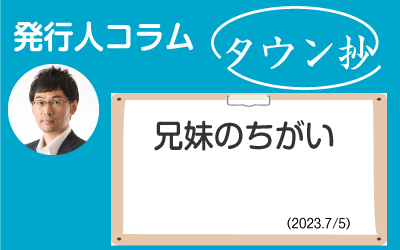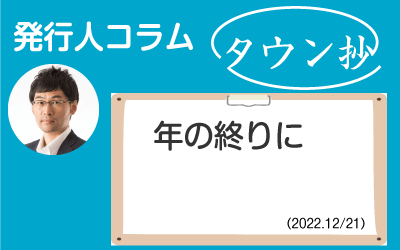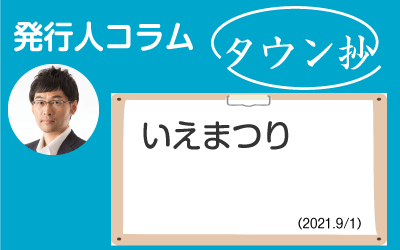高1の息子を夏休み中に短期留学させようと試みたが、学校と行政のプログラムの抽選に漏れ、結局諦めた。コロナ禍明けの長期休暇で、例年以上に希望者が多かったようだ。民間業者を頼る手もあったが、来年改めて学校のコースに申し込むことにした。
となると、この夏をどう有意義に過ごすかが問題となったが、私としては受験を終えたこのタイミングで外国に触れてほしく、考えた末、家族でシンガポールに出かけてきた。英語が公用語であること、安全であること、比較的行きやすいことなどから、家族で出かけるにはちょうど良かった。
シンガポールについては、同国に長く滞在し、現在は日本の食の国際化(ハラールやベジタリアン対応等)のコンサルティングをしている横山真也さんの著書『おいしいダイバーシティ』(ころから)の編集を手伝ったことがあり、同国の魅力を多岐にわたって聞いていた。中国系、インド系、アラブ系などさまざまな民族が入り混じる東京都23区ほどの国土しかない国がいかにして世界有数の金融都市になれたか。それは、地域活性化や地域コミュニティを見続けている私にとっても大きな関心事で、一度は訪ねてみたい国ではあった。
結論を言えば、居心地の良い国だと思った。多民族国家ゆえ、相手が何者なのか、何語を母語とするのか――そうしたことが「分からない」を前提にしており、排他性を感じさせない。良い意味でスタンダードがなく、それによる自由さがあることを知った。
さて、小学生の娘に旅の感想を聞いたときのこと。都市の機能性、特に地下鉄の利便性の高さには私も感心していたのだが、「地下鉄の駅で風がなくてびっくりした」と言ったのに驚いた。駅が壁に覆われていたのを、目による認知ではなく、体で感じたのだろう。私にはない感性で、目を見開かれる思いをした。
コミュニティの第一歩は、他者との違いを認め合うことから。そんな基本を、旅先でも帰国後も、学ばされる夏となった。