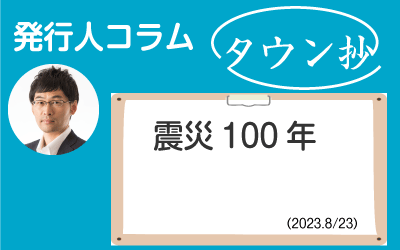吉村昭の名著『関東大震災』は、巨大地震発生を予見する学者同士の対立から始まる。「百年周期説」を唱えて学会で異端視された学者が、実際に巨大地震に直面して目を輝かせる場面は印象的だ。
100年というのは何においても大きな節目だが、地震の場合は少し意味が異なる。先例のように百年周期説に相応の説得力があることを思うと、この100年間に関東を襲う大震災が起こらなかったのは幸運だったというしかない。私たちは本気で備えるときを迎えている。
となると、やはり学ぶべきは歴史になる。現代のライフスタイルに照らせば、東日本大震災や阪神・淡路大震災などから学ぶことが多いが、同じエリアで起こった関東大震災もまた、多くの教訓を残してくれている。
その第一は、火災だ。関東大震災では、東京市で5万2178人が焼死し、土地の約43%(日本橋区に至っては1坪残らず全域)が消失したというが、住宅の密集度などを考えると、その恐れは、現代のこの地域にも当てはまる。特集記事(記事リンク)で紹介したようにこの地域は被害が少なかったわけだが、その大きな理由は農村地域で大規模火災が発生しなかったことにあるといえる。
火災被害というと本所被服廠跡が有名だが(3万8015人が死亡したとされる)、被害が広がった一因に、避難者が持ち込んだ荷物に着火したことがあるという。荷車に載せた荷物は橋を渡る際などにも問題になったようで、必要最低限の荷物で避難すべきことを教えてくれる。
流言飛語も私たちが警戒すべきことだろう。日常でもフェイクニュースが出回る時代である。情報へのリテラシーを日頃から意識していなければなるまい。
そんな思いから、地域紙なりに特集記事を企画した(記事リンク)。何かのヒントになれば。