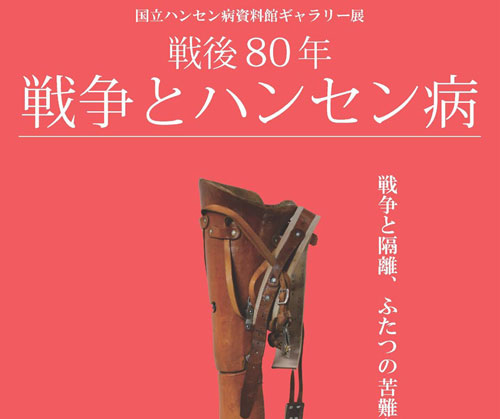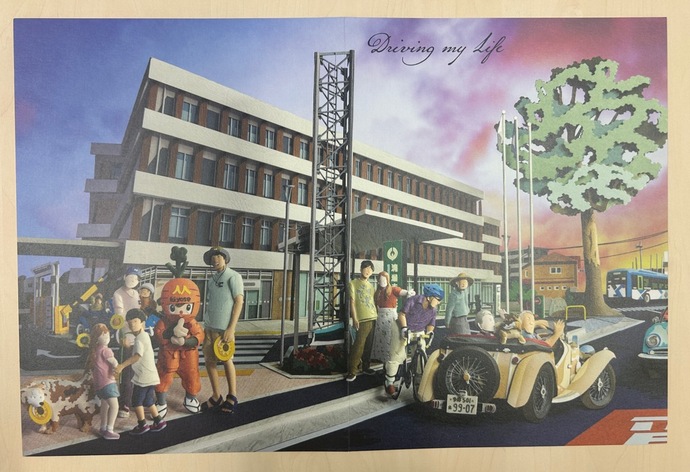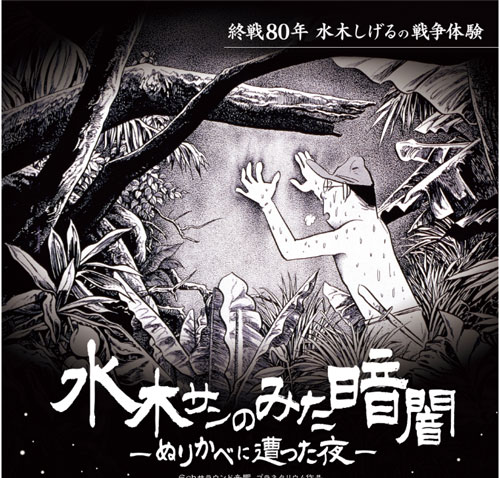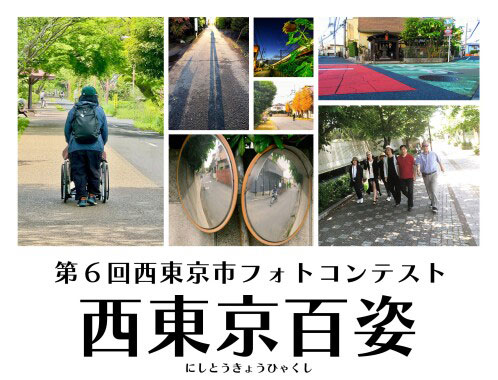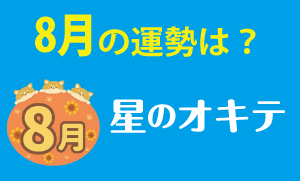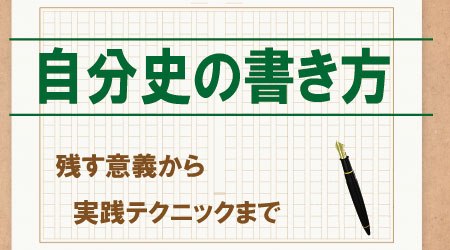新座れきしてらすで武士体験、姫さま装束
「こどもの日」の兜飾りの記憶も新しい5月11日(日)、新座市れきしてらす(歴史民俗資料館)で甲冑や姫さま装束の体験会が開かれた。
朝から多くの親子連れが訪れ、50組以上が甲冑に身を包んだ。中には、武士の格好で「えいえいおー!」と勝どきを挙げるグループも。会場は笑顔であふれた。

企画に協力をしたのは、武蔵村山市を拠点に活動する「武士団・村山党の会」。
14年前に、地域ゆかりの「武士」でまちおこしをしようと発足した会で、今回のような装束体験会のほか、甲冑姿でのイベントへの参加、寸劇、手作り甲冑教室などを多彩に行っている。また、「ロックでPRしよう!」とバンド「武士団村山党」も結成している。「武蔵村山のアピールをして皆さんの笑顔が見たい! 呼ばれればどこへでも行きます!」とのスタンスで、今回は、同館の学芸員とのつながりを縁に、新座市まで出張した。
「自前の甲冑を着込む団体は各地にあるのですが、『武士団・村山党の会』は、自分たちで甲冑を作っているのが特徴的です。今回は、平安時代の頃のスタイルから、鎌倉時代、戦国時代と歴史ごとの甲冑を持ち込んでくださいました」
と、同会の活動を評価する、同館の学芸員・寺内良夫さん。この企画については、「甲冑を実際に着るという体験から、歴史への興味が広がればと期待しています」と狙いを話す。

武士団「村山党」とは
そもそも「武士団・村山党」とは何だろうか。
同会で広報を担当する貞儀憲さんによると、平安時代末期に荘園の守護を目的に現在の武蔵村山市・瑞穂町あたりで発足した武士団のこと。後に、周辺地域に勢力を広げ、「村山党」となった。現在の関東地方の各所にあった武士団を総称する「武蔵七党」の一つ。各時代で、保元の乱、承久の乱、子孫たちは戦国時代に八王子合戦などにも参陣している。
「有名な武将がいたり、印象的な事件があったり、大きな城が築かれたというわけではないですが、確実に地域に武士がいて、しかもその歴史が長いのです。私たちはそのことを、学術的に研究するというのではなく、文化として現代によみがえらせ、楽しみながら触れていくことを目指しています」
と貞さん。
ちなみに、当サイトのメインエリアの一つである小平市との縁では、江戸時代に小平地域を開拓した小川九郎兵衛が村山郷の出身。そうしたこともあり、同会は、同市の「アーティストバンクこだいら」にも登録して、時折、小平エリアでも活動している。

工夫のたまものの「手作り甲冑」
ところで、気になるのは自分たちで製作しているという甲冑のことだが、どのように作っているのだろうか。
「文献や資料を見ながら、独学でノウハウを築いてきました。材料は違いますが、できるだけ実物と同じ技法を用いています」
そう説明してくれたのは、甲冑製作を担当する徳田茂宗さん。武蔵村山市の「魅力マイスター」にも登録される徳田さんは、日頃、甲冑教室の指導なども担っている。
その徳田さんによると、材料はプラスティック板を用いることが多いとのこと。あるいは紙を貼り合わせるなどして、甲冑の基盤を作る。プラスティック板を使うときは、熱湯につけて柔らかくしてから型を取るなど、時間も手間もかけるという。
また、兜はヘルメットを土台に、プラスティック板などを張り付けて飾りを作る。
いずれも、それぞれのパーツを紐で結び合わせていくのが見栄えと強度の上で重要だ。
1セットを作るのに、概ね半年がかかる。ちなみに費用は、6~7万円。参考までに、完成品を購入すると数十万円が相場だそうだ。
「発見したことやノウハウは、今後作る人たちの参考になるように記録に残している。研究し、工夫しながら作っていくのが楽しいですね」
と徳田さん。

同会の活動や、甲冑教室については、同会(TEL:090-3811-0613)へ。
[リンク]


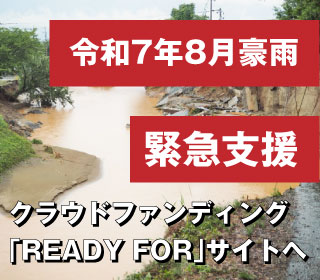



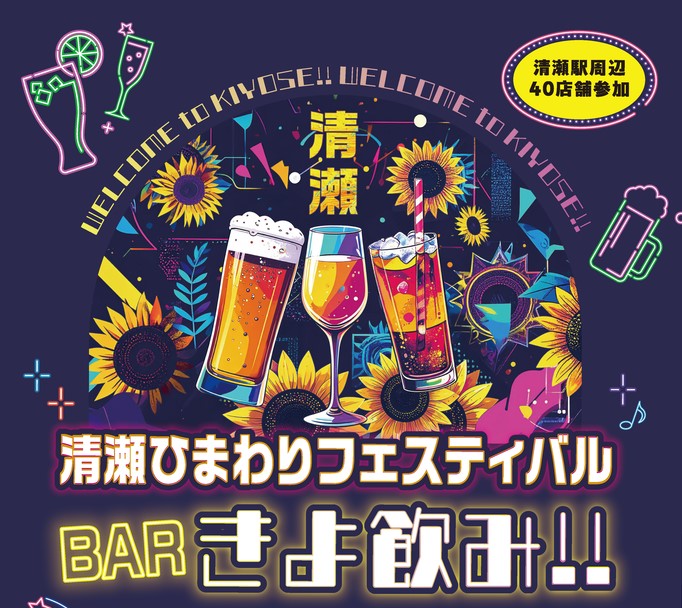
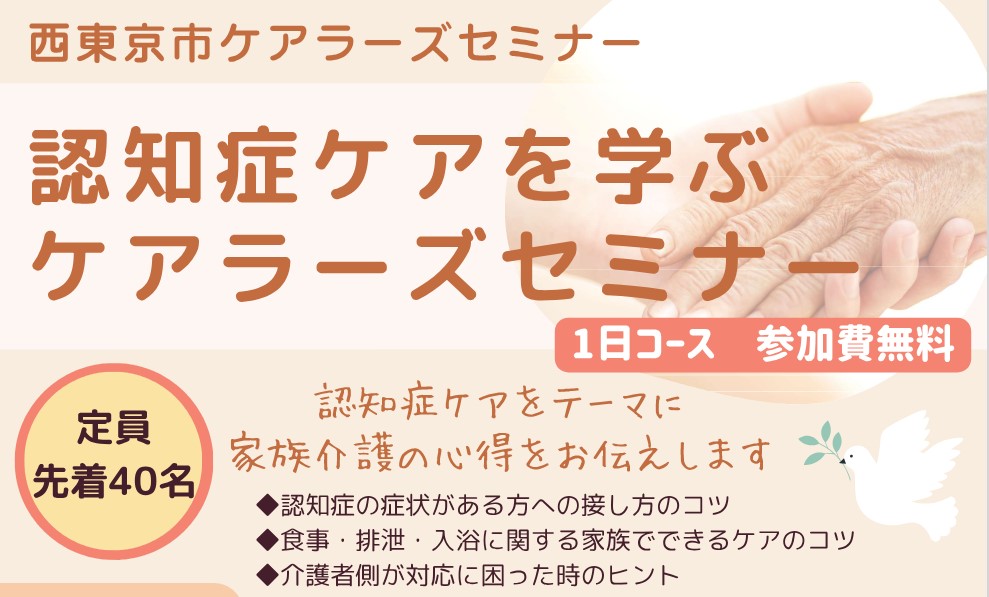
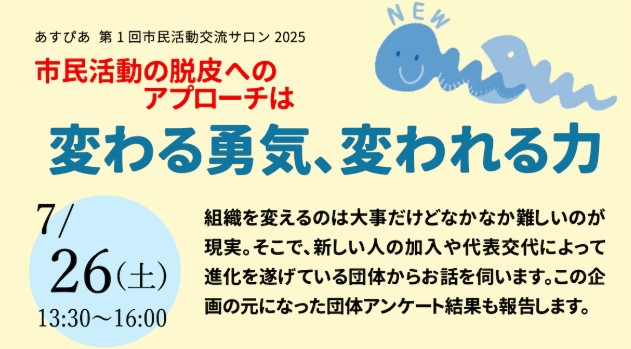



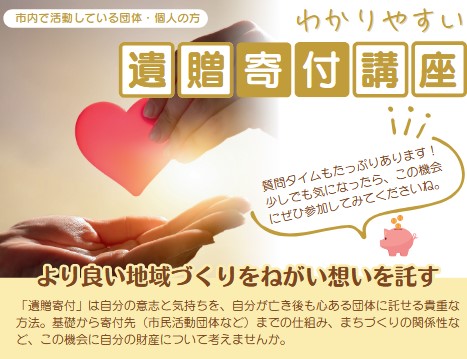

-scaled.jpg)