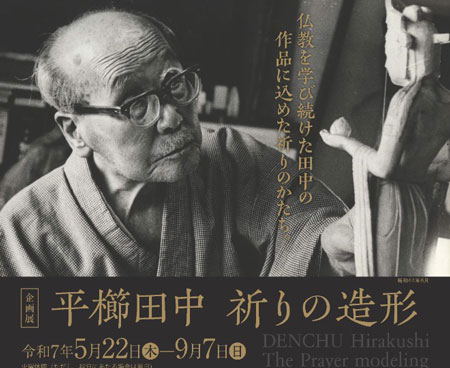昨秋(2024年秋)、小平市平櫛田中彫刻美術館の学芸員・藤井明さんによる、国内では初の図鑑となる『明治・大正・昭和 メダル全史』が出版された。6年を掛けた力作で、メダルとは何かという本質的な機能の考察とともに、美術的価値も紹介している。執筆のきっかけは、同館での企画展だ。

選挙啓発やグリコのおまけなど、エピソード豊富に
オリンピックでおなじみの「メダル」だが、実はその機能・役割は多種多様だ。皇族の節目の記念や、博覧会・品評会での授与、会社の周年事業、従軍記章――。
「『名誉』や『記憶』といった面が大きいですが、はっきりした定義はありません。そこがメダルの面白さですね」
と、著者の藤井さん。意外なところでは、啓発などで活用されている。例えば1930年の「帝都復興記念」メダルは、関東大震災が発生した11時58分を示す時計と共に、「緩む心のねじをまけ」の警句が刻印されている。
また、コレクションにつながりやすいのもメダルの一面だ。代表的なのは「グリコのおまけ」。特に歴史上の人物が人気を集め、楠木正成と西郷隆盛は60万個もの製造に至ったという。
ほかに、1936年の杉並区の区議選挙では、投票した人に特製メダルを配ったところ、他区よりも投票率が高くなったという史実がある。
小平に暮らした齋藤素巌も多数制作
こうしたメダルの機能やエピソードに触れる一方で、同書では、畑正吉や日名子実三といったメダル製作に貢献した彫刻家も多数紹介している。その中には、小平市で後半生を過ごし、作品が市内で多数展示されている齋藤素巌(そがん)も名を連ねている。
出版は、平櫛田中彫刻美術館での企画展がきっかけ
藤井さん自身がメダルに関心を持ったのは、2014年に、平櫛田中と親交のあった藤井浩祐の企画展を開いたこと。メダルのコレクターと接点ができ、3年後に特別展「メダルの魅力」を開催すると、東京大学の関連団体から賞が贈られるなど反響を呼び、出版の話が持ち上がった。
そのように着手してから6年。コロナ禍で取材に動けない時期もあり、思った以上に難航した。
「メダルについては参考になる文献自体がなく、情報を集めるのに苦労しました」
と藤井さん。書籍のために気になるメダルを集めていったら、いつの間にか約200個を所有するメダルコレクターになっていたという。「コレクターの自覚はまったくなかったのですが」という藤井さんは、写真教室にも通い、書籍用の写真の大半を自室で撮った。約280点収録。まさしく渾身の一冊だ。
1万3200円の高価な本だが、「まずは記録として残せてほっとしています。写真を眺めるだけでも楽しめる本なので、少しでもメダルに興味を持っていただければうれしいです」と藤井さんは話している。
B5判、256ページ、国書刊行会。
【リンク】