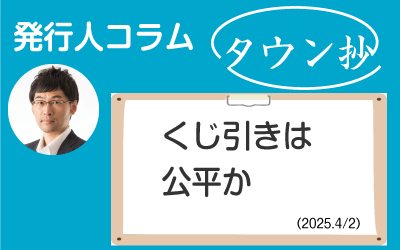6日(2025年4月6日)投開票の小平市長選挙に合わせて「小平こども選挙」が実施されている(関連記事)。
その取り組みの一場面で子どもたちから「獲得票が同数だったらどうなるんですか?」という質問が出た。
答えはくじ引き。ただ、やり方は自治体の定めによる。引くのも、当人だったり選挙長だったりするし、順番も、届出順もあれば、順を決めるくじ引きをするところもある。
これらは全て公平性を期した苦肉の策なのだろうが、よく考えてみたら、「公平」というのはかなり疑わしいものだ。
さて、そんな例を引っ張り出したのは、読者の一人からPTAの役員決めの話を聞いたからだ。その方は現在、中学校のPTAの副会長をしているそうで、来季の役員決めの進行を担当した。
選出方法は、まずは立候補。不足があった場合に、全員でくじ引きとなる。
実際のところ、立候補で決まることはほぼない。そこでくじ引きとなるのだが、欠席者の分は進行役が代理で行う。引く順番は名前の五十音順にするか、そのときの席順か。進行役の判断次第。ケチの付け所満載だ。
そんななかで問題が起こった。用意したくじが一人分多く、しかもその当たりくじが最後に残ったのだという。
当然、もう一度引き直すべきだろうが、「間違った運営が悪い」と頑として応じない人が複数人。最終的には居たたまれずに立候補する人が出て、丸く(?)収まった。
PTAに限らず、地域がらみの役員決めはとかく難しい。最近の本欄の志向として「ややこしいことはAIに」としたいところだが、それはそれでケチの付くものだろう。
ちなみに、チャットGPTに「学校のPTA役員の決め方」と問うと、「学校や地域の特性に合わせて柔軟に決めることが大切」と答えが来た。
だから、それが分からないから聞いてんじゃん!