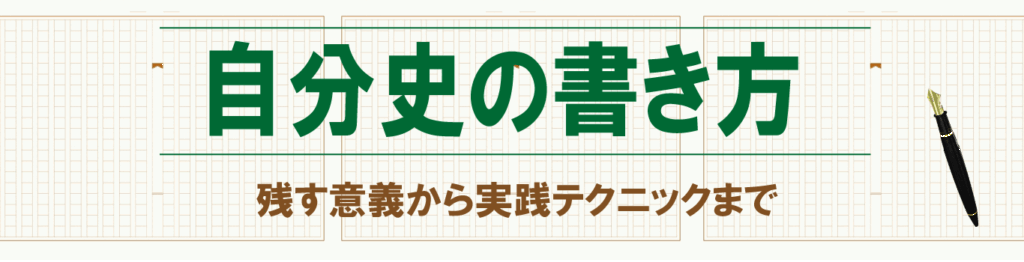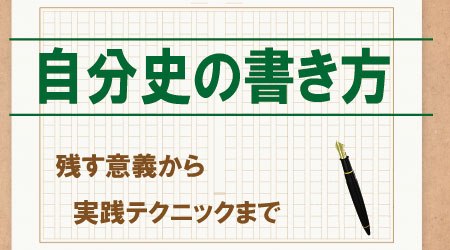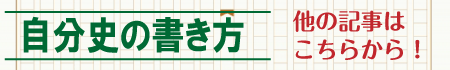前回までの2回で、書き手の意識の持ち方を指摘した。今回は視点を変えて、「自分史」の社会的意義について考えてみる。
「自分史に50万円なんてばかげているよ!」
本人は作る気満々でも、自分史作成の契約間際になって、家族の反対で頓挫するケースは珍しくない。そのように頓挫する方は、ほとんど皆、板挟みにあったような苦しげな表情を浮かべる。
結局のところ、「自分史を作る」という行為を社会化できないため、特に実子たちから「自己満足」「虚栄心」などと責められると、尻込みせざるを得なくなるわけだ。「自分の金だから自由だ」と主張をしたところで、「だまされている」「ぼったくられている」と言われると、適正価格が分からないため反論もできない。
「社会化」などと書いたが、難しいことではない。要は「なぜ必要なのか」「なぜ書き残したいと思うのか」をきちんと説明できるかどうかだ。ここが明確でないと、前回指摘した「誰も読まないよ」に反論できないことになる。
ちょっと発想を変えてみよう。
自分史に興味を持つ人は「残したい」と自分主体に考えるわけだが、「自分史は家族から必要とされている」と真逆から見てはどうだろうか。
実は今の時代ほど自分史が求められているときはないといえる。なぜか。社会(家族)が分断化しているからだ。
私はいつもセミナーで「テレビ」を例に取るのだが、シニア世代に「子どもの頃、家にテレビはありましたか?」と聞くと、「いや、なかった」の返答が来る。その状況から、まず町に1台、次に一家に1台となる。そして、部屋に1台、ついにはスマートフォンで一人1台、の時代に変遷する。
こうした時代の変遷について、小平市にある白梅学園大学の元教授で著書も多数ある教育学者・汐見稔幸さんは「サザエさんからドラえもんの時代へ」とユニークに表現している。サザエさんでは、三世代が一つの家に住み、親戚のノリスケさん一家や隣家の伊佐坂さん、三河屋さんら商店街の人々など、多数の人たちとの交流が描かれる。それが、時代が下るドラえもんでは、大人と子どもの世界が線引きされ、シニア世代および幼児の登場はほとんどなく、子どもの関係でさえごく少数のいつものメンバーに限られる。
この流れを受けてさらに展開すれば、現代のアニメから見えるものはさらに「狭い世界」となる。一時期大流行した(そして、なぜか急激に失速した)妖怪ウォッチに至ると、「オレの友達、出てこい、〇〇!」といった具合で、友達すら自己都合で「管理」ができるようになる。あのウォッチは、スマホのデフォルメと考えるべきだろう。
若干話はそれたが、やはりテレビに話を戻すと分かりやすい。一家に1台の時代ならば皆で同じ番組を見、笑い、流行歌に夢中になれた。しかし、テレビが個人のものになっていくと、「共有」されるものがなくなっていく。今では、親子が見ている番組はまるで違う。番組を通して世界の一端を知っていくとするなら、各人の間でまるで違う世界を生きているということになる。結果、関心事自体が重ならなくなる。もし親子の間の会話が減少しているとするなら、それは「大人になったから」などということではなく、共有するものが失われたからといえるだろう。
今、買い物先、移動場所、食事、地域とのつながり――など、活動時間や行動範囲の違いにより、日常における家族間の接点は失われ続けている。結果、たとえ一緒に暮らしていても、本当に大事なことが共有されていないという状況に陥る。
こうしたなかで、「自分史」は家族間・大切な人の間での「共有」を取り戻す力を持っている。
詳しくは次回に譲ろう。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にご相談ください。(TEL:042-497-6561、メール)