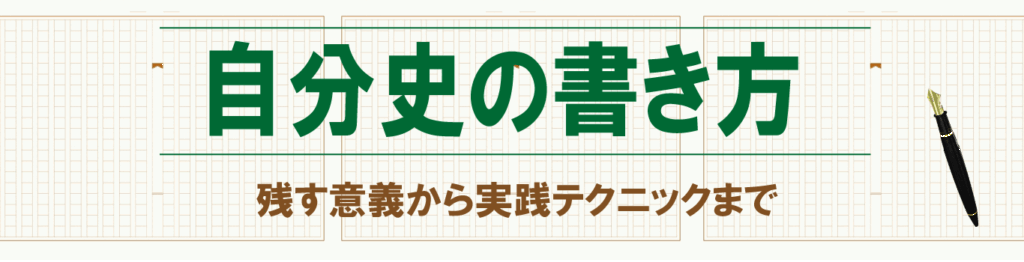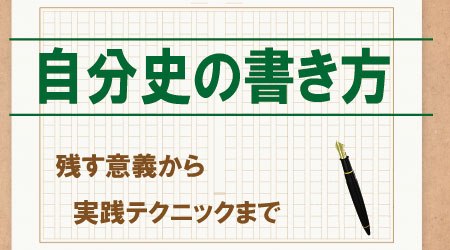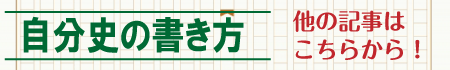自分史セミナーを開き出してすぐ、私たちはあることに気付かされた。
「家族のことを書きたい」
そういう方があまりにも多いということにだ。
「自分史」を文字通りに解釈すれば、そのテーマは自分の人生であり、家族のそれではない。しかし、「家族をテーマに」と真剣に口にするのは一人二人ではなかった。もしかして、私たちが見落としている何かがあるのではないか――。
そこで私たちは一旦、セミナープログラムを見直し、参加者たちのニーズを探り直した。
従来語られている自分史の効力には、以下のようなものがある。
◎記録
◎コミュニケーションツール
◎人生哲学・価値観・教訓などの継承
◎子孫へのメッセージ
◎人生の棚卸し
◎交流の機会
◎楽しみ、生きがい
「記録」「継承」については言うまでもないが、自分史はただ「残す」ことだけが目的ではない。むしろ、コミュニケーションツールとして「活かす」ことのほうに、個人が自分史を手がける意義はある。
前号では、すれ違いが避けられない社会構造を指摘したが、「自分史」を持ち出したとき、本質に迫る会話はしやすくなる。「本質」とは言うまでもなく、人生観や家族の歴史、そして将来構想のことである。
自分史というと多くの人が、「自分史=人生のまとめ」という図式を思い浮かべるが、その認識は必ずしも正しくない。もちろん、そうした意識から手がける人もいるだろうが、自分史の理想的なあり方は、これからの人生に役立てるものである。前述のコミュニケーションツールはその一つであるし、自分を見つめ直す機会という点も大きい。これについては、次号で私自身の体験を語ろう。
「家族」を書く動機
さて、ここで冒頭の問いに戻る。なぜ、家族を書きたいという人が多いのか。
ここまで読んでくださった読者ならすでにピンと来ていることと思うが、この文脈で考えるならば、一種のイニシエーションとして捉えることが可能だろう。つまり、「絆」の再構築、あるいは、承認のための作業である。
分断が進む社会の中でよりどころとなるはずの家族。しかし、その家族とすら、本当の絆を築けていないのではないか。
そのような不安が(無意識にでも)あるとき、それを顕在化したいと望むのは当然のことである。自分史――あるいは家族史、の体裁を取って執筆・発行したとき、その過程および発行時に家族と本質的な議論ができ、かつ、共有物として完成品を手元に置くことができる。それは、確かに家族を結びつけ直すものとなる。
むろん、家族と過ごした時間を「記録」して残したいという純粋な動機や、まったく逆に、何らかの欠落感を埋め合わせるために記憶をたどる必要があるというケースもあるだろう。家族の形はさまざまであり、家族の数だけ動機はある。
ただ、家族に焦点を合わせたとき、自ずと「絆」がテーマになることは間違いない。家族史に関心がある方なら、執筆時にそのことを意識するよう勧めたい。
次号では、今回の視点を持ちつつ、私自身が自分史を作ったときの体験を語ろう。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
◇
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。