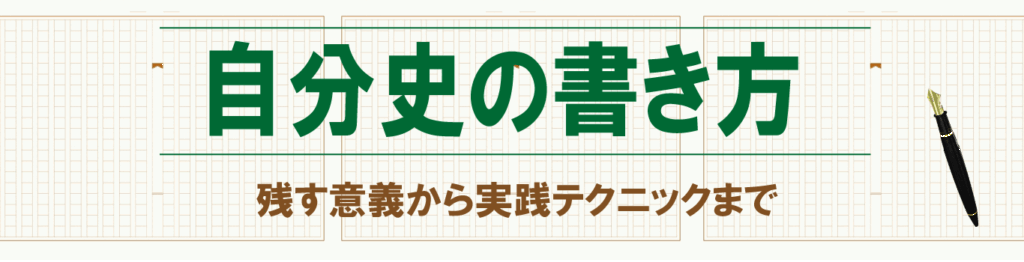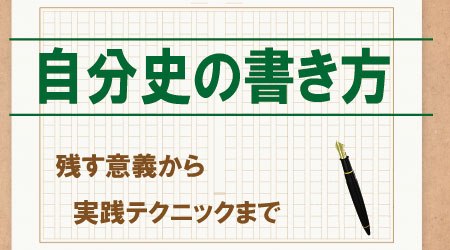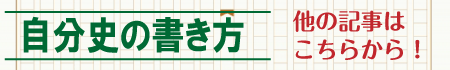前回は「とにかく原稿を書くこと」の大切さを指摘した。今回は、多くの人から寄せられる「書いたって誰も読まないよ」の不安を乗り越えるための方法を考える。
「書いたって誰も……」
この問いに答えるのは非常に難しい。
「いや、そんなことはないですよ。きっと読まれますよ!」
そう言うのは簡単だが、誠実な回答ではない。
誰も読まないかもしれない――。その恐れはどんな文章にもある。私だって、今書いているこの文章が誰にも読まれないかもしれない、という不安を抱えている。だからこそ、少しでも読んでもらえるように、分かりやすい言葉を使い、構成を考え、誤字がないように気を配る。
この観点からいえば、きちんとした文章は(※厳密には「きちんと書こうとされた文章」は)、この不安があることによって書かれる、ともいえる。その意味では、「読まれないかも」の不安もポジティブに受け止めたい。
セミナー参加者の声 「何を書いても、ウチの息子たちは…」
「いや、私が言いたいのはそんなことではないんだよ……」
そう声を上げたい方もいるだろう。
言いたいことは分かる。以前、セミナーに参加してくださった男性がこんなことを語っていた。
「私が何を書いてもね、ウチの息子たちは、『また、親父が美談ばっかり並べているよ』としか思わないだろうよ」
確かにそういうケースもあるだろう。そこは、書き手・読み手の関係性による。
「良い文章」を書けば誰からも評価される、と思っている人が少なくないが、実際はそうではない。時に正確な記述はその正確さゆえにつまらないものになるし、言葉足らずの文章のほうが激しく想像力を刺激することもある。それならば文章への評価はどう決まるのかといえば、それは往々にして書き手と読み手の関係性によるところが大きい。
このように説明するとコムズカシくなるが、言っていることは単純に過ぎない。例えば、記者は報道として記事を書く。コラムニストはのびのびと見解を語れる立場でコラムを書く。行政マンは正確さを重視して公的文書を書き、詩人は言葉の可能性を模索して書く。もし記者が詩人のように書けば、読者は「この記者は報道というものが分かっていない」とすぐに見切ることだろう。
手紙のように自分史を
では、自分史はどのように書けばよいのか。
考え方はいろいろあるが、私たちは「手紙のように」と提唱している。
もちろん、自分の人生を一つの「大作」にまとめたい、という人もいるだろう。もしそうしたいのなら、それは小説として書いたほうがいい。
いわゆる自分史の枠の中で、10人から20人程度の親族・友人に手渡したいというものなら、彼らの顔を思い浮かべながら手紙のつもりで書いていくと思いが届きやすい。手紙のように書かれたものは、受け取る側も自分に向けて書かれたものとして読む。ここには、「誰も読まない」という不安は存在しない。
作家デビュー裏話
少し話はそれるが、「タウン通信」でエッセーを連載してくださっている小説家の志賀泉さんは、代表作『指の音楽』を書き上げたとき、実はそれを最後の作品にするつもりだったという。40代まで小説家として芽が出なかったためで、最後の作品をお世話になった人に届けたいとの思いで筆を執り、手紙のようなつもりで書いたのだそうだ。結果、それが太宰治文学賞を受賞し、小説家としてのデビュー作となった。
これは極端な例だが、やはり誰かに自分の思いを届けたいのなら、読者の顔を思い浮かべながら書いていくことが近道となる。その技術的なところは、連載の後半で紹介する。
さて、ここまで紙幅を費やしたが、実はまだ問題は解決していない。「誰も読まないよ」の問いに対する答えは、ほかにもある。
次号、別の視点からこの点を追究していこう。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。