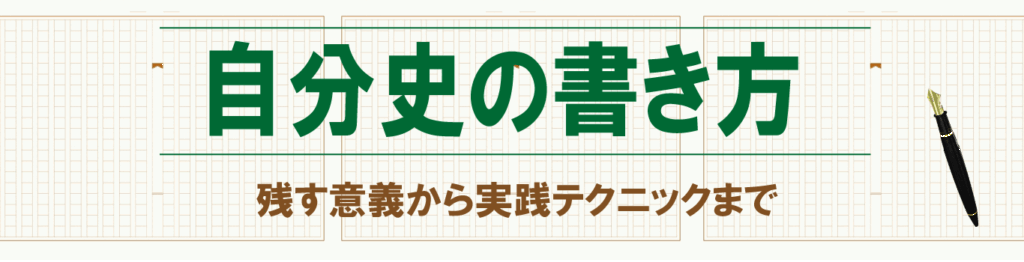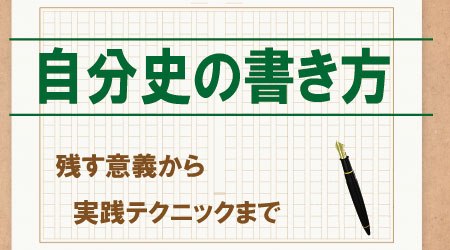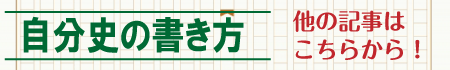「タウン通信」では、月に1、2回のペースで「自分史セミナー」を開いてきた。毎回、多くの方にご参加いただき、「自分史」への関心の高さを感じている。
そこで「タウン通信」では、より多くの方にノウハウをお伝えするべく、当ウェブサイト上にて、「セミナー」を展開することにした。
セミナーは全11回に上る。ぜひ、「自分だけの一冊」を作るための参考にしてほしい。

セミナーでよく出るセリフ
さっそく、本題に入ろう。
セミナーを開催していると、ほとんど毎回ぶつけられる質問がある。
「お金を掛けてまで作る意味があるんですかね?」
これだ。
もしかしたら彼らは、この質問をぶつけたくてセミナーに参加してきているのかもしれない。自分史に興味はあるけれども、作ったところでどうなるのだろうか……。そんなふうに一人で逡巡している人たちには、セミナーは疑問をぶつける格好の場だろう。
しかし、大変僭越な言い方になるが、これは質問の相手を間違えている。なぜなら私たちの答えはあまりにも明確だからだ。
「意味は大いにあります」
そう答えるに決まっている。そう思っていないのならセミナーなど開いたりはしない。
では、どのような意味があるのだろうか。その答えは、連載を読み終えていただいたときに掴んでいただけているはずだ。
まずは初回となる今回は、上記の問いの一つの重大要素である「お金」を切り口に、話を進めていこう。
「お金」を考えることで見えてくるもの
「自分の人生を表現するのにお金を掛けるのは無駄ですか?」
「タウン通信」には自分史制作のパートナー会社があるのだが、その代表者は前述の質問を受けるといつもそのように問い返している。
なるほど、大切なものにお金を投ずるのが望ましい消費とするなら、この反問はごく自然なものといえる。なにしろ、人にとって自分の人生以上に価値のあるものなどないはずなのだから。
私はそこまで強い言い方はしたくないが、やはり、ある程度の出費は覚悟すべきだろうと考えている(後述するが、費用を掛けない方法もある)。
ある程度の出費とは、製本代と取材費である。
ただし、今の時代は割安に製本をすることが可能であり、本当にミニマムで考えるなら数万円あればそこそこ形にはなる。
数万円でどの程度の本が作れるかといえば、例えば、A5判、50ページ、モノクロ、10部といったレベルになる。本というよりは冊子と呼ぶべきもので、人生をつづるには少々淡白な作りだが、それでも「活字」になる喜びは得られるだろう。
「その程度なら自分でパソコンで作るよ」
そうおっしゃる方もいる。パソコンを自由に操れるなら、それもいい。印刷機を自由に使えるなら、複数部を製作することも可能だろう(ただし、インク代などで結果的に高くつくケースもある)。また、プリントパックなどネット印刷への入稿も自分でできるなら、上記で紹介した冊子などを自力で手掛けることもできる。最初から最後まで自分で作った! という作る喜びを最も感じられるやり方だといえる。
もう一つ。ノートに手書きでつづる、という手もある。これは1冊のみしか残せないが、だからこそ価値がある、という考え方もできる。この場合は、ノート代程度の出費で済む。
このように選択肢を挙げてみると、実はお金のことはさしたる問題ではないことが分かってくる。自分史を本にするには100万円以上、場合によって数百万円がかかる、と思い込んでいる方が多いが、結局のところ、どこまでを求めるかで費用は変わる。「書店に流通させなきゃ意味がない」「日経や小学館などの大手系列で出版したい」などの規模やブランドを重視するなら数百万円の支出を前提とするべきだが、「残したい」という一点で自分史を検討するなら、いちばん大切なのは、まずは原稿を書くことだ。費用への懸念が執筆を遠ざけてはいけない。
「でも、書いたところで誰も読まないよ…」
この意見を受けることも多い。次回は、その問いに答えていこう。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。