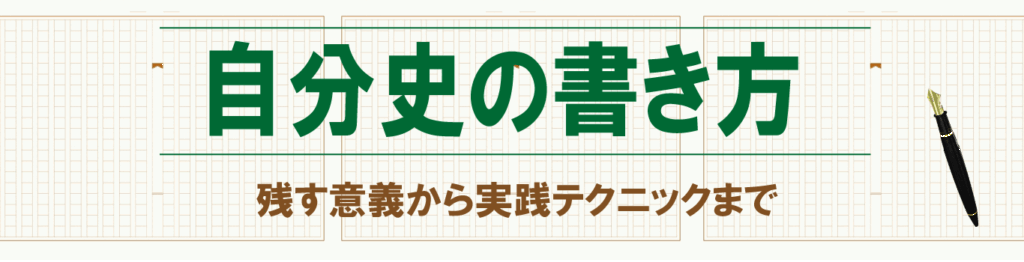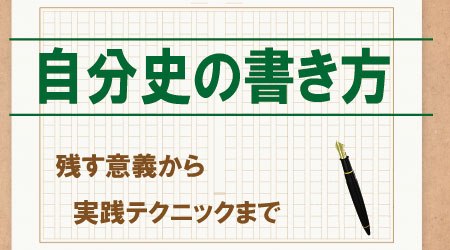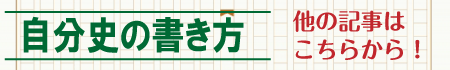リアルに開催してきた「自分史作成セミナー」をウェブで紹介している「自分史・ウェブセミナー」。ここまで自分史の意義、必要性などを語ってきたが、今回からは具体的な技術面に入ろう。
「どう書けば良いか分からないんだよね~」
実際のセミナーで、ほぼ毎回聞くコメントに「どう書けば」「何を書けば」「どこから書けば」というものがある。
そうなる原因は実ははっきりしている。書くことがあいまいになっているせいだ。
いや、そんなことはない。私の人生のことを書くのだから、書くべき内容ははっきり分かっている。
「あいまい」などと指摘されたら、多くの人がそう答えることだろう。
しかし、具体的に追及していけば、分かっているようで分かっていない、ということがはっきりしてくる。
「結婚のときのことを書きたい」としても、「では、結婚の何を?」となると、「?」と立ち止まる人が少なくない。
文章は料理と同じ
文章について語るとき、私はいつも料理を例に取る。同じ趣旨の本も出ているが、実際、文章と料理はよく似ていると思う。
料理の場合、メニュー決定には2つの道筋がある。一つは最初から決めている場合。「子どもたちのリクエストに応えてカレーにしよう!」というケースだ。
もう一つは、在庫を見て決めるケース。冷蔵庫の中に豚肉、ジャガイモ、ニンジン、タマネギがある。ここから何が作れるか? 肉じゃが? シチュー? そうだ、カレールーのストックがあったからカレーにしよう――と、そんなパターン。
文章も同じで、最初からテーマを決めるケースもあれば、材料を見比べて書く方向を決めることもある。例えば新型コロナウイルスを例にした場合、「終息のシナリオ」とテーマ設定して、それに合わせて材料を集める(取材する)こともあれば、今分かっている材料の中から「新型コロナウイルスの時代に私が感じたこと」などの文章を書くこともできる。
さて、自分史の場合は、言うまでもなく、スタンスは後者になる。つまり、ある程度材料がそろっていて、それを使って書くということだ。
しかし、冷蔵庫に全ての材料があるとは限らないのと同様、「何かが欠けている」ということがあり得る。食材で足りないものがあれば買い出しに行くように、文章でも、「買い出し」をしなければいけない。それが取材だ。
取材の詳細は次回に譲るが、「買い出し」をするときに意識しておくべきことがある。どんな「料理」(=文章)にするかを、あらかじめイメージしておくことだ。
同じカレーでも、甘口もあれば辛口もあり、さらにキーマカレーやシーフードカレーなどとさまざまに種類がある。言うまでもなく、キーマカレーとシーフードカレーでは、買う材料が異なる。
どんな文章を書きたいのかのイメージがないまま取材をしても、よい材料は得られない。そしてそれは、書くべきことのあいまいさが続くことを意味する。
従って、自分史執筆においては、①材料を整理する→②完成をイメージする→③不足の材料を補う(取材する)、という工程が最初の段階で必要ということになる。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。