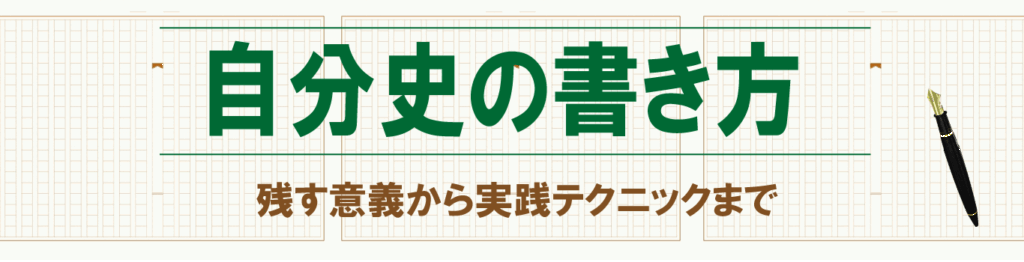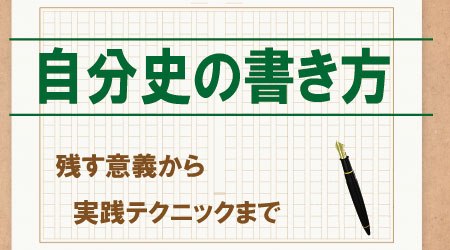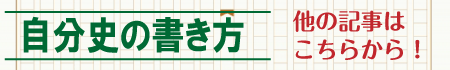前回は、書き始める前に材料を集めることが大切だと紹介した。では、それをどのように集めるのか。今回は「取材」についてまとめる。
さて、材料集めの段階となった。いわゆる「取材」を行うわけだが、別に構える必要はない。
「取材」なる単語はニュース番組やドラマなどで重々しく使われる傾向があり、何か特別な響きがあるが、実際にやっていることはさほど大それたことではない。
取材の方法は、大きく3つに分けられる。
一つは記録に当たること。もう一つは、現場を訪ねること。そしてもう一つは、人に話を聞くということだ。
自分史に当てはめた場合、記録に該当するのは、写真、日記、手紙などになる。自分が書いたものだけを見返すのか、あるいは、家族や友人の書いたものにまで当たるのかは、どういうものを書き残したいのかによる。
次に現場を訪ねることだが、これはかつて暮らした家や地域、勤めた職場、思い出の場所などをめぐることになる。むろん歳月のなかで風景は様変わりしていることだろうが、現場に立って初めて思い出すことや気付くことがある。「どうせ景色は変わっている」などと軽んじてはいけない。出掛けてみると、ばったりかつての友人に出会うなど、思わぬ縁がつながることもある。
インタビューの肝
前述の2つは、どちらを先に行ってもよい。ただ、3つめとなる「人に聞く」は、基本的には前述2つの後に行う取材となる。その理由を記す前に、インタビューで何を聞くのかについて語ろう。
実際のセミナーでは、私はその場で参加者へのインタビューをしてみせるのだが、例えば以下のような簡単なことを聞く。
「どこから来ました?」
「歩き? 車ですか?」
「雨で大変だったでしょう?」
「自分史を作ることについては、どう思っていますか?」
適当に質問しているように思うだろうが、ここで私は意識的に2種類の質問を行っている。そして実はインタビューとは、この2種類を繰り返すことでしかない。
前半の2つの質問は、「事実の確認」を行っている。そして後半2つは、どう感じていたのか、何を考えているのか、という主観を尋ねている。
事実を確認し、それについてどう思っているのかを聞く。基本的にインタビューは、この繰り返しになる。専門的にはこれを「2つのF」などという。Fact(事実)とFeeling(感情)の頭文字を取ったものだ。ともあれ、質問はこの2種類に分けられると知っていると、質問を整理して組み立てることができる。
――と、ここまで説明すれば、先ほどの問いの答えは明らかだろう。
記録に当たれるものは先に自分で調べておき、ある程度事実をそろえたうえでインタビューを行うほうが、その中身は濃いものになる。その場で「あれはどうだっけ?」と事実確認するのは時間が惜しい。「日記にこうあったのだけど、どう思う?」などと聞くほうが有意義だ。
自分史においてのインタビュー相手は、基本的には家族や友人になる。ぜひ気軽に「取材」をしてみてほしい。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。