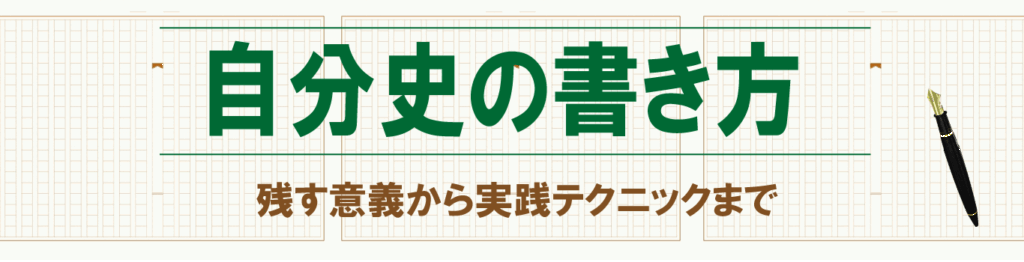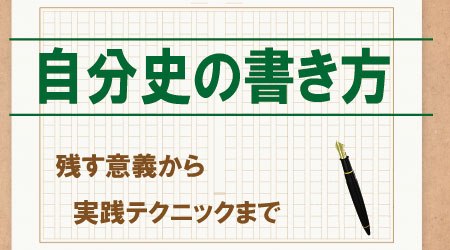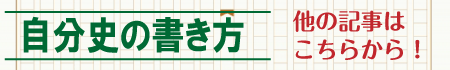前回に続き、どのように文章を書けばよいか考えてみよう。
文章は料理に似ていると何度もお伝えしてきた。今回も、料理を例にしよう。
例えばテレビ番組を見ていて、見たことのない食材が出てきたとする。「うわー、何ですか、これぇ⁉」とレポーター。そこで始まるのが、いわゆる食レポだ。そのとき、こんな食レポだったならどうだろう?
「ええっ! なに⁉ この匂い。すごい不思議な感じ。(口に入れてみて)ああ……。すっごい変わった味ですねぇ~。歯ごたえも独特です」
これで何かが伝わっただろうか。
食レポも文章も、求められる役割は同じだ。それは、「それを知らない人にそれが何であるかを伝える」ということ。「それ」の対象が、事実、思想、心情などの差異こそあれ、知らない人に知ってもらうという点では、何ら変わりはない。
では、その役割を果たすには何が必要なのか。細かいことまで言い出せばキリがないが、最も重視すべきことを挙げるとするなら、私は「具体性」と言いたい。
先の食レポの例のように、曖昧な表現では何も伝わらない。おいしいのなら、どうおいしいのか。甘いのか辛いのか、何かに似ているのか。
味覚は主観のため、表現は難しいのだが、せめて、「イチゴとメロンを足したような匂い。味はブドウに似てますね」ぐらいは言いたいところだ。
人生で一番…
さて、具体性の話をするとき、私はいつもセミナーで、次の問いを出す。
「今まで食べたものの中で一番おいしかったものは何ですか?」
これまでに、さまざまなユニークな回答に出会ってきた。印象的なものを少し挙げよう。
「まだ1ドル360円だった時代に仕事でハワイに出掛けたんだけどね。ようやく着いたホテルで、パイナップルが出てね。よく冷えたパイナップルに、塩がかかっていて……。そりゃあ、うまかったねぇ~」
「登山中に雨に降られて、体も冷えきってようやく下山したことがあるのですが、着いた山小屋でカップラーメンを食べたんです。お餅を入れて。あれは忘れられません」
どちらも具体的で、場面が立ち上がってくる。とりわけ、前者では「1ドル360円の時代」や「塩」が、後者では「お餅を入れた」という具体性が際立っている。
皆さんもぜひ、「一番おいしかった食べ物」を振り返ってみてほしい。そのとき脳裏に浮かぶのは、単に「食べ物」ではなく、シーン(場面)となっているはずだ。
その一つ一つを丁寧に記述すれば、読者にイメージを共有してもらえる。とにかく具体性を積み重ねること。他者により正確に何かを伝えるには、それが近道だ。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。