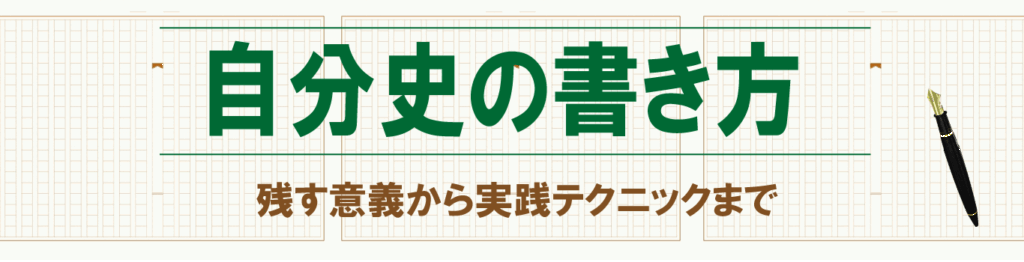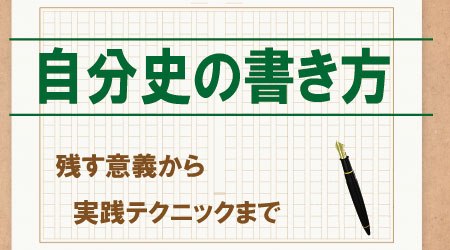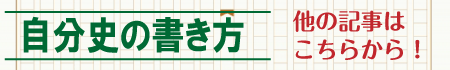「技術編」として、4回にわたり取材や書き方について触れてきた。その最終段階として、今回は表現と校正について語ろう。「書く」という作業での最終段階となる、表現、そして校正について考えてみたい。
「推敲」の故事を持ち出すまでもないだろうが、文章というのは基本的に、一旦書いてから「読み返す」「表現を磨く」という作業が伴う。ここをおろそかにすると、表現の未熟さにとどまらず、誤字だらけのひどい原稿になってしまう。
文章のうまい人は一度でビシッと決まった文章を書ける――と思っている人が少なくないが、実際はプロほど読み返す。プロの場合は、さらに編集者の目が入り、校正者のチェックを受ける。自分史では(多くの場合)一人で書き上げるため、より慎重に原稿を見直すことが重要だ。
見直しで注意すべき点
では、どのように原稿を見直したらいいのだろうか。
親族・友人にだけ配る自分史ならばそこまで神経質になる必要はないが、せめて以下の点くらいは注意しておきたい。
【誤字等はないか】
単純に文字が抜けるというミスが意外に多い。例えば、「思いました」を「思いした」など。
【他者を傷つけていないか】
文章では、無意識に他者を傷つけてしまうことがある。例えば、笑い話のつもりで「そのとき母に死ねと言われ、本当に傷つきました」と書いた場合、母からすれば「なぜ書き残す必要があるの?」と心に傷が残る。
【事実かどうか】
たとえ少部数の自分史でも、事実でないことを断定するのは避けたい。「子どもが10人いた」と「子どもが約10人(例えば9人)いた」は決して同じことではない。
間違えやすいポイントは
最後に、間違えやすいポイントを指摘しておこう。
▼固有名詞〈特に人の名前は、思い込みで間違ったまま書き残す恐れがある〉
▼見出しやキャプション〈本文は読み返しても、見出しの文字を見過ごすケースは多い〉
▼目次〈目次を入れる場合、ページ数がずれているケースが散見する〉
どんなに優れた文章を書いても、誤字があるだけでその信ぴょう性は一気に下がる。神経質になり過ぎてはいけないが、できるだけ正確に書き残すようにしよう。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。