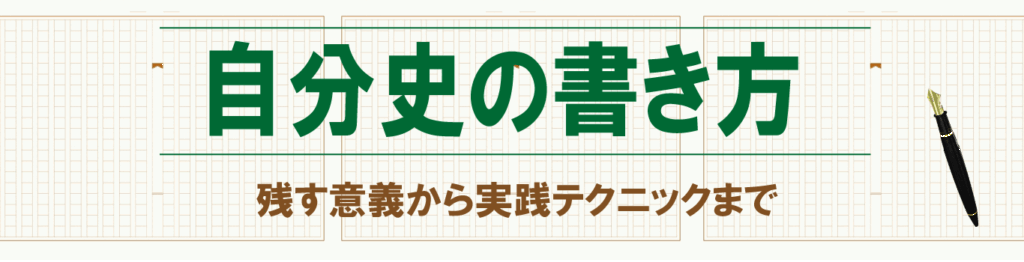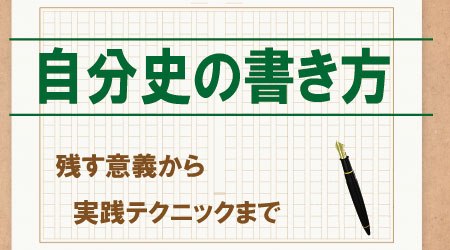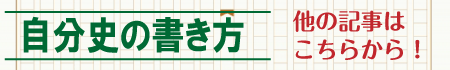全11回にわたって連載した「自分史の書き方」。連載を終えてしばらくしてから、「なぜ地域紙の会社が自分史を作るのか? そこが伝わってこなかった」といった声をいただいた。
なるほど、確かにご指摘の通りだ。
実はこのウェブサイト上で展開した「自分史の書き方」は、「タウン通信」が紙で発行している「地域紙」で連載したものをベースにしている。地域紙上ではリアル開催の「自分史セミナー」などの案内もしていたため、取り組みをイチから説明する必要を感じなかったが、確かにウェブサイトで初めて読んだ方には、「なぜ地域紙が?」「実績はあるの?」と疑問に思えたことだろう。今回は「番外編」として、当社の取り組みの一端をご紹介したい。
最初は読者の要望から始まった
まずは「タウン通信」がなぜ自分史制作を手掛けているかを説明しよう。
といっても、これについては特段の理由はない。「技術的にできるから」というのがいちばんの答えになる。
きっかけは15年以上前の、ある読者からの要望だった。
「お宅はカタログ制作とかチラシを作ったりもしているのだから、自分史も作れるでしょ?」
言われてみれば、工程は同じである。原稿を用意し、デザインし、組版で本の体裁に整え、印刷所に入稿し、納品に至る。作るだけなら、新たに取り入れるものは何もない。
というわけで、その方の制作をきっかけに、何となく頼られるままに自分史を作るようになっていった。自分史づくりが少し流行っていた頃でもあった。
転機は、Kさんの死
そうやって5、6冊手掛けた頃だっただろうか。自分史への向き合い方を大きく揺さぶられる出来事があった。Kさんの死だ。
Kさん――ここでは名前は伏せるが、文化系の市民活動に取り組み、行政との関わりも深く、西東京市ではそこそこ名の通った88歳の男性だった。その取り組みやイベント告知などを地域紙で取り上げることも多く、私(執筆者・谷)は月に1度は顔を合わせていた。
あるとき、Kさんが言った。
「自分史というか、短歌をまとめたいのだけど……」
ややはにかんだように切り出したその時のことは、今も鮮明に覚えている。
「短歌を作っているのですか?」
知らなかったので問い返すと、「まあ、今も時々やるけど……。それよりも、昔作った短歌をまとめたいんだ。兵隊だった頃の……」
「兵隊!?」
そこからの話はとても興味深かった。
Kさんは出征したビルマで捕虜となったが、収容所で生活した約1年半の間、演劇などの文化活動の担当者になったという。また、行軍中は手製のノートを肌身離さず持ち歩き、短歌を書き連ねていた。つまりは戦地に文化活動があったということで、その話からは、文化活動がいかに人間に不可欠なものなのかが感じられた。
ともあれ、Kさんには行軍中や捕虜の頃に書き溜めた短歌が多数あり、それをきちんと本の形で残したいというご希望があった。
打ち合わせでご自宅に伺うと、押し入れの中から手製のノートを十数冊出してくださった。大半はわら半紙を糸で綴ったもので、持ち歩いたと思われる手のひら大の小さなものが何冊かあった。
そのうちの幾つかを開き、特にKさんは、現地の売店の女の子の話をした。たぶん10代後半の女性だろう。その子を詠った短歌が幾つもあった。戦地でそうした交流があったこと自体が私には驚きだった。一方で、ほとんど一晩中、川の中を行軍したという話も聞いた。相当に過酷な体験で、語るのもつらそうだったが、ざっと見たところ、それに触れた短歌はなかった。行軍についていけなくなり自決した仲間もいたそうで、Kさんは涙を浮かべながらその話もしてくださった。その場面を詠った短歌は、幾つかあった。
短歌をテーマ別にまとめるか、時系列でまとめるか――といったような打ち合わせをして、次週にまた訪ねる約束をし、その日は辞去した。そして、翌週に訪ねたときに初めて、脳梗塞(だったと記憶している)で倒れ入院していると告げられた。
結局意識は回復せず、病院に運び込まれて10日ほどで他界された。奥様とも面識があったが、ご葬儀後に奥様は「体がしっかりしていたから、心臓が強くて10日も頑張れた」というようなお話をしてくださった。
私には、無力感が残った。行軍の合間に書き連ねた短歌の数々は、Kさんにとって何にも代えがたい、言うなれば人生そのもののようなものであって、それを活字にし製本することは心の奥底にずっとあった念願だったはずだ。その念願を叶える一歩を踏み出したそのときに、突然に命が尽きてしまった。もう少し早く取り掛かっていたら――という思いが、私の中に強く残った。
「自分史を作りましょう」。積極的にそう呼びかけるようになったのは、それからだ。少しでも「書きたい」という気持ちがあるなら、早いということは絶対にない。リアルで開催した自分史セミナーには二十歳の女性が参加してくれたことがあったが、彼女は「今までの人生を見直し、書いたものを母に渡したい」と参加動機を教えてくれた。
Kさんが指し示すように、自分史を作ることは、文化活動そのものである。文化活動が人生を彩り、人間を豊かにする。先のKさんへのインタビュー記事では、タイトルを「戦争に耐える文化の力」と付けた。つらい日々、つまらない日常も、私たちは文化活動を通して光あるものに変えられる。そして、作り上げたものを他者と共有し語り合うこともまた、人間関係に潤いをもたらす文化の力だ。
もう一人、古谷さんのこと
長い原稿になってしまうが、最後にもう一人、古谷康之さんのことを触れておこう。
古谷さんは西東京市谷戸町で書店経営などをされた方で、当サイトでは、「東京大空襲と隅田川慰霊」について回顧談を掲載させていただいている。
➡「東京大空襲で人生が変わった――。谷戸の86歳男性が振り返る」
古谷さんは晩年、がんを発症し、余命1年と告げられた。「年を越せない」と言われた春先に「自分史を作りたいんだ」とご自宅に招かれた。書店経営をされただけあって、本や活字がお好きらしく、すでに原稿の大半は整っていた。「あと、幾つか書き足したいんだ」とおっしゃり、時間の制限があるため、古谷さんの執筆と並行して、仕上がっている原稿の編集作業を進めた。
かなり大急ぎで2カ月ほどで自分史を納品し、その後、古谷さんは旧知の方にお送りになられた。その本をきっかけに幾人もの人と旧交を温めることができたようだ。むろん、自分史送付の際に余命に触れられたのが大きかったのだとは思うが。しかし、自分史の存在は、便りを出す絶好の理由になったことだろう。
「年を越せない」と言われた古谷さんだったが、ご家族で正月を迎えられ、暑くなり出した頃に亡くなられた。訃報を受け、ご自宅を訪ねたところ、ご遺影の前に『道』とタイトルを付けた自分史が置かれていた。弔問に来られた方が、手に取って偲んでいくという。
「実は最初は反対していたのだけど、この自分史は最後に作れて本当に良かった」
と奥様からお言葉を頂いた。私としては何か、Kさんに頂いた宿題をようやく果たせたような気分になった。
自分史というと、思いが溢れてまとめきれないというケースが少なくないが、まずは着手し、時間があるなら何度だって作っていけば良いのだと思う。1回で、大作・傑作を作る必要なんてまったくない。もっと気軽に、もっと自然体で、まずは手を動かしていく。やっていくうちに、次第に整理されていくということも少なくない。
皆さんのそうした活動のうえで、「地域紙」というのは、身近なサポーターになれる存在だと考えている。ぜひ気軽に、「タウン通信」を頼ってほしい。
(文/「タウン通信」代表・谷隆一)
※「タウン通信」では、製本までは行いますが、書籍の流通・販売は手掛けていません。部数や体裁(ハードカバーなど)はどのようにでも対応可能です。
※本紙では自分史作成の相談に随時応じています。当社は西東京市にありますが、遠方の方もお気軽にお問い合わせください(TEL:042-497-6561、メール)。